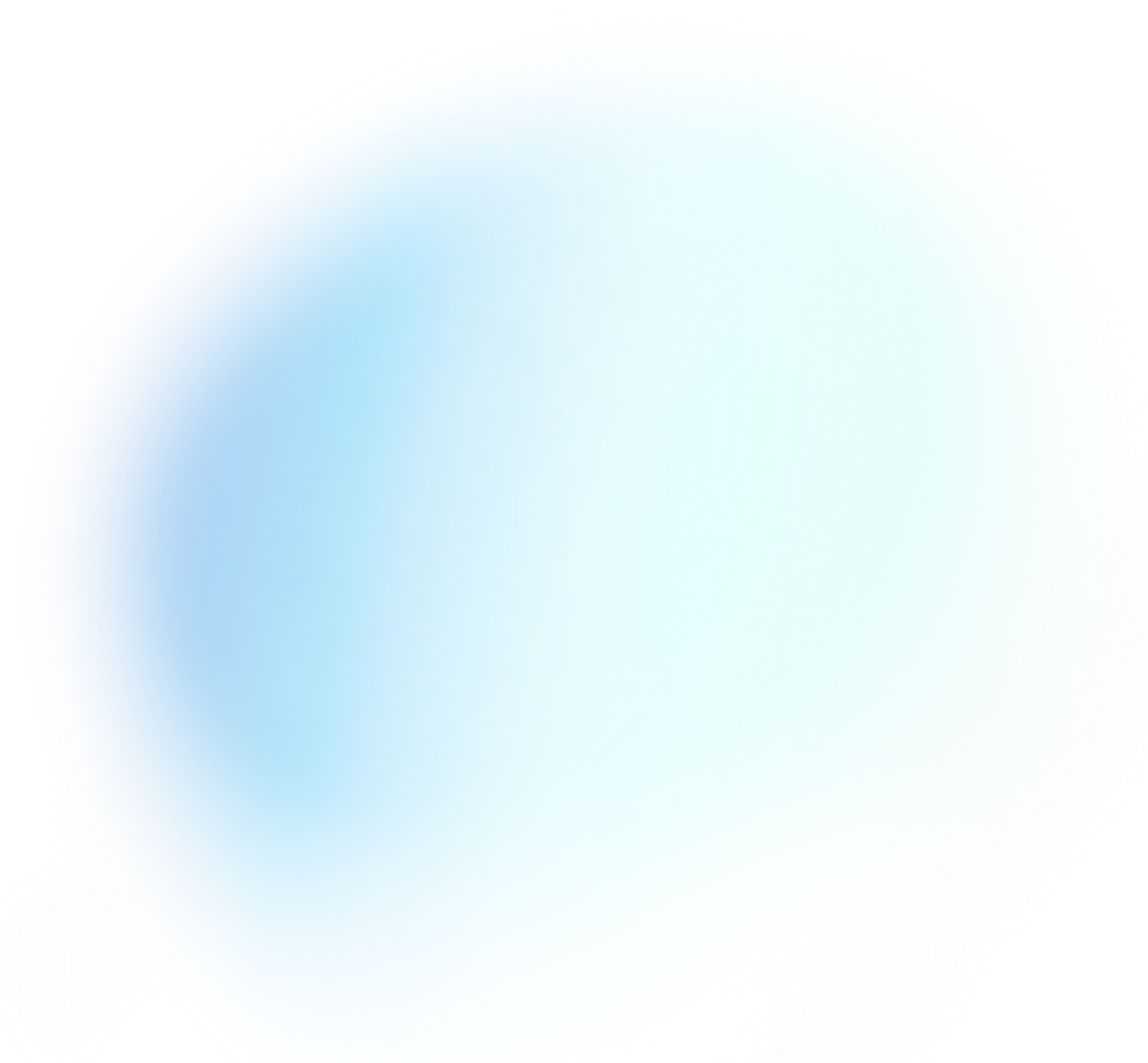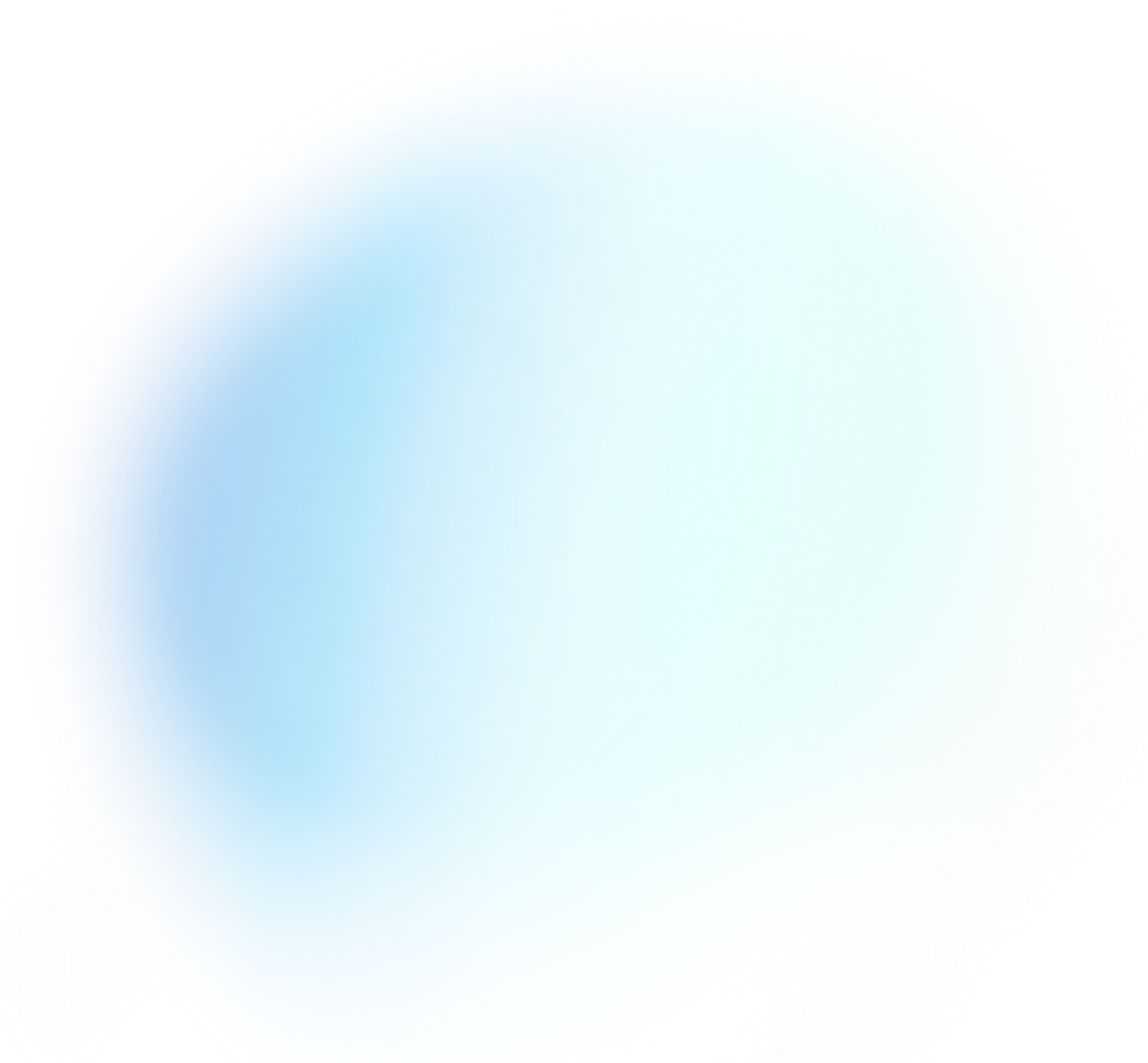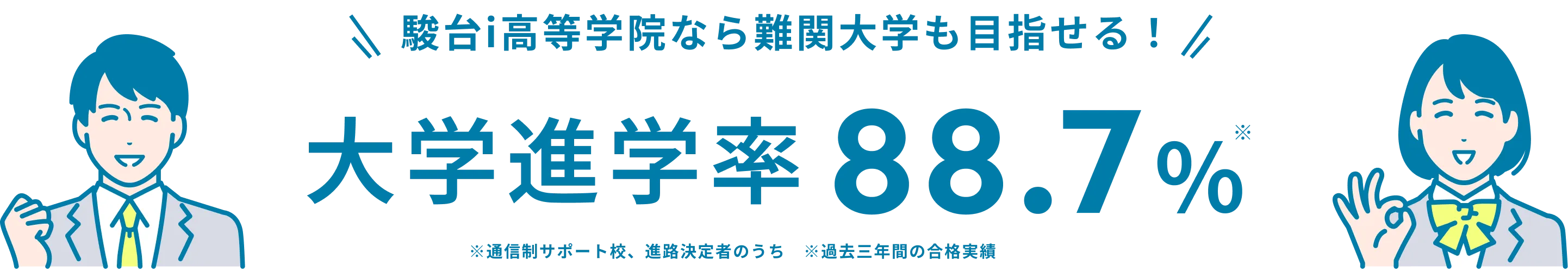
大学進学率 88.7%
合格大学一覧
-
国公立
-
東京大学
大阪大学
九州大学
筑波大学
琉球大学
一橋大学 -
北見工業大学
秋田県立大学
山形大学
都留文科大学
山梨大学
長野大学 -
静岡県立大学
名古屋工業大学
愛知県立大学
京都教育大学
奈良女子大学
福岡女子大学
-
東京大学
-
私立
-
慶應義塾大学
早稲田大学
上智大学
東京理科大学
青山学院大学
明治大学
学習院大学
立教大学
日本大学 -
中央大学
法政大学
駒澤大学
東洋大学
獨協大学
専修大学
南山大学
中京大学
同志社大学 -
立命館大学
熊谷大学
関西学院大学
甲南大学
関西大学
京都産業大学
近畿大学
関西外国語大学
-
慶應義塾大学
-
専門学校
医療福祉・医療衛生・IT・情報・プログラミング・ゲーム・観光・服飾・自動車・動物福祉・鉄道・教育福祉・鉄道・教育福祉・調理・調理製菓・スポーツ・建設系・音楽・アミューズメント・簿記系・コンピュータ等の専門学校 -
留学
-
テキサス大学
ネバダ大学 -
オークランド大学
ペンシルバニア大学
-
テキサス大学

※駿台甲府高校通信制の進学大学(過去3年間の実績)
VOICE
卒業生の声
-
VOICE.01

駿台と出会い、
大阪大学 外国語学部 國定芽依さん
一歩前へ踏み出せた。自由な学生生活を送れるこの高校への転校を決断しました。
受験勉強や趣味、バイトに割ける時間が増え、スクーリングを通して友人との交流も十分に深められたため良い学生生活を送れました。
自習室は学習に集中できる上に、先生方がいる日は気軽に雑談や相談ができるので息抜きにもなりました。
また、先生もどんな質問や添削にも快く応えてくださるので、塾のように学習サポートが充実していると実感しました。
志望大学は文系大学であるにもかかわらず苦手料目の数学の配点が高かったため苦労しましたが、やはり基礎の徹底が克服への近道だと考えます。
1次試験でもれないため、足切りをくらわないように適度に対策しながらも2次試験のための勉強にも注力するのは、学習のバランスが取りにくく大変でした。
大学では音楽系のサークルに所属し、1年次から受講できるゼミで商業における実用的な力を身につけたいです。
駿台には転入という形での入学になりましたが、最後までサポートしてくださった学校関係者の方々には深く感謝しています。 -
VOICE.02

自分にあった生活と
一橋大学 商学部 S.Hさん
学びの両立ができる私は体調不良が悪化し、学校に行きたくても行けない状況となり、当時は不本意ながら通信制への転校を決めました。
転校当初は勉強どころではなく、堕落した生活を送っていました。少し前へ踏み出せる契機となったのは、高2の頃に芸大を目指す決心をし、
ピアノのコンクールなどに出場したことです。通信制に通っていたからこそ日中の時間を確保でき、ピアノの練習に集中できました。
高2の冬頃には、自分の中で音楽の道に絞ることに違和感を覚え始め、やはり勉強で進学しようと決心しました。
しかし、そこからすぐにはスイッチが入らず、自分の体調を優先しつつ勉強を始めました。独学で勉強する数料も多く、自習と学校の映像講座などを併用し、
塾は週1回通程度でしたが、効果的な学習ができました。横試では、夏まではE判定ばかりでしたが、自分のペースで勉強を進めて、
共通テストで理想より得点できなかったものの、2次で巻き返し、合格することができました。
通信制に移るまでの学校に登校できなかった期間は、その罪悪感で生きているのがただただ辛かったです。
しかし、通信制という場所で自分のペースで勉強を進められたことに大変感謝しています。この経験を糧にして、苦しんでいる人に寄り添える人になれるよう努力しようと思います。 -
VOICE.03

進学に向けた
名古屋工業大学 工学部 大森貴史さん
環境の充実私は全日制の高校に入学したのですが、環境になじめず2年生のときに通信制への転入を決意しました。
私は大学に進学したいと考えていたので、受験環境が整っている駿台に転入しました。
入った当初は、勉強の習慣が全くなく、生活習慣もあまりよくない状態でしたが、担任の先生と相談しつつ、少しずつ勉強を始めていきました。
通信制高校の学習は基本的に自学自習で日々の多くの時間を自分で自由に使うことができるので、無理なく習慣作りができたと思います。
3年生の受験期に入ってからは、実践的な学習をし、模試を定期的な目標にしつつ自学自習の習慣を徹底していきました。
時には体調を崩すこともありましたが、着実に成績を伸ばすことができ、無事に第一志望の大学に合格することができました。
受験というものは精神的に負担のかかるもので大変ではありましたが、通信制の環境のおかげで自分としては
決して無理をすることはなく努力を続けることができたと思います。
これからの大学生活ではこの努力の経験を活かして、主体的な学習を続けていきたいと思います。